- PDNレクチャーとは?
- Chapter1 PEG
- Chapter2 経腸栄養
- Chapter3 静脈栄養
- 1.末梢静脈栄養法(PPN)
- 1.1 PPNの特徴と適応
- 1.2 PPN製剤の種類と適応
- 1.3 PPNカテーテルの種類
- 1.4 PPNカテーテルの留置と管理
- 2.中心静脈栄養法(TPN)
- 2.1 TPNの特徴と適応
- 2.2 CVカテーテルの種類
- 2.3 CVカテーテル留置法
- 2.4 皮下埋め込み式CVポートと
その留置法 - 2.5 PICCとその留置法
- 2.6 エコーガイド下での
CVカテーテル留置法 - 2.7 TPN時の使用機材
- 2.8 TPN基本液とキット製剤の種類と特徴
- 2.9 アミノ酸製剤の種類と特徴
- 2.10 脂肪乳剤の種類と特徴
- 2.11 TPN用ビタミン製剤の種類と特徴
- 2.12 微量元素製剤の種類と特徴
- 2.13 TPNの実際の投与方法と管理
- 2.14 TPNの合併症
- 2.15 特殊病態下のTPN
- 2.16 小児のTPN
- 2.17 TPN輸液の調製方法
- 2.18 HPN(在宅経静脈栄養)
- Chapter4 摂食・嚥下リハビリ
- PDNレクチャーご利用にあたって

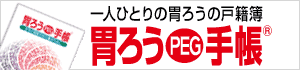
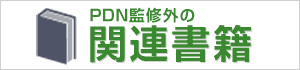

TPN施行中の合併症はカテーテルによる機械的合併症と代謝的合併症、そして感染に大別することができる(表1)。機械的合併症はカテーテルの長期間留置に起因する合併症で、代謝的合併症は高浸透圧かつ大量の栄養素が静脈内に直接投与されるために生じる合併症である。感染はカテーテル関連血流感染が重要であり、いずれもTPNを管理していく上で必要不可欠な知識である。
カテーテルによる機械的合併症 血栓形成、カテーテル先端位置異常、Extravasation of fluids、静脈壁穿孔、不整脈、空気塞栓、事故抜去、カテーテル破損、カテーテル閉塞など 代謝的合併症 糖質関連(高血糖、低血糖)、アミノ酸関連、脂質関連(必須脂肪酸欠乏、高脂血症)、電解質異常、微量元素関連(欠乏症、過剰症)ビタミン関連(ビタミンB1欠乏症)など 感染 カテーテル関連血流感染症(CRBSI)、トンネル感染 |
1.機械的合併症
1.1 血栓形成
カテーテル留置中はカテーテル周囲(フィブリン鞘)や血管壁に血栓(壁在血栓)が形成される。特に前者はカテーテルが留置されていれば、必ず形成されていると考えて良い。特にポリエチレン、テフロン製のカテーテルで形成されやすく、ポリウレタン、シリコン製のカテーテルでも形成される。
壁在血栓が大きくなってくると、カテーテル周囲血栓と癒合し、上大静脈などの深部静脈が徐々に閉塞することがある。通常は側副血行路の発達により無症状のことが多いが、急性閉塞はその限りではない。またカテーテル周囲血栓はカテーテル先端を覆うため、弁として作用することがあり、逆血不可能となることがある。またこの血栓に流血流の細菌が付着すると感染巣となり、カテーテル血流関連感染症を発生する可能性もあり、これが血栓形成における最大の問題である。
予防には抗血栓性カテーテルを用いることであるが、それでは完全には血栓形成を阻止できないため、予防的にヘパリンやワーファリンを投与することもある。
血栓形成に対する治療は、留置カテーテルの抜去が原則である。血栓の溶解の目的でウロキナーゼ(6,000単位/ml)を利用することもあるが、基本的には溶解は不可能と考えるべきである。却って、溶解して血栓が遊離した場合、肺塞栓となることも考えられる。
1.2 カテーテル先端位置異常
カテーテルの固定糸がはずれて、気がつかないうちに抜浅したりすることがある。また小児におけるカテーテルの長期留置では、成長に伴って徐々に浅くなっていることもある。柔軟なカテーテル(シリコン製など)は自然にカテーテルの位置が移動することもある(mislodging)。定期的に胸部X線写真を撮影して、先端位置を確認しておく必要がある。
1.3 Extravasation of fluids
カテーテルの先端が血管壁に接触している状態で高張液を投与した場合、その輸液が血管外に漏出する現象をいう。前述のカテーテルの先端位置異常に伴うことが多いが、正しい位置に先端があっても起こりうる合併症である。高浸透圧の輸液が血管内皮細胞に接触すると内皮細胞は障害を受け、血管透過性が亢進して輸液が血管外に漏れ出して局所の疼痛や腫脹を訴えることある。皮下に漏出するような場合は発赤、腫脹などの炎症所見を呈するが、胸腔内に漏出すれば胸水貯留、心周囲に漏出すれば心タンポナーデを来すこともある。基本的に発見したらカテーテルを抜去することが原則である。
1.4 静脈壁穿孔
カテーテル先端の位置異常の問題で、ポリウレタン製の硬いカテーテルによって静脈壁が長期間圧迫を受けた場合、静脈壁が穿孔することがある。上大静脈に起こった場合は上述のextravasationと同じように胸水貯留などで発見されることもある。基本的に発見したらカテーテルを抜去し、厳重な経過観察を要する。穿孔部は自然閉鎖することが多いが、胸腔内に輸液が漏出している場合は胸腔ドレナージを要することもある。
1.5 不整脈
カテーテルが深く入りすぎて、右心房、右心室を刺激し不整脈が発生することがある。特にポリウレタン製の硬いカテーテルで誘発されやすい。カテーテル挿入時もガイドワイヤーによる刺激で不整脈を発生することもある。
1.6 カテーテルの破損、閉塞
カテーテルの破損により、輸液が漏出することがある。とくにシリコン製のカテーテルで起こりやすく、固定時に針で少し突いただけでも破損の原因になるため、注意が必要である。長期留置用のBroviacやHickmannカテーテルでは体外に出ている箇所の破損であれば、repair kitを使用して修復可能である。このようなカテーテルを鎖骨下穿刺法で挿入した場合、カテーテルが鎖骨と第1肋骨の間で圧座されて(pinch-off)、断裂を来たすことがある(catherter fracture)ので、胸部単純X線写真でカテーテルが鎖骨と第1肋骨の間で狭小化しているかを確認する必要がある。
またカテーテルの閉塞は先に述べたカテーテル内に血液が逆流して血栓が形成されたことによることが多く、生理食塩水でのフラッシュなどが試みられる。長期管理では、脂肪乳剤、ヘパリンなどによる閉塞がよく知られている。脂肪乳剤とヘパリンは混合すると凝固することが知られており、脂肪乳剤の使用前後はヘパリンではなく、必ず生理食塩水でのフラッシュを行うことが重要である。
2.代謝的合併症
2.1 糖質関連(高血糖・低血糖)
糖代謝異常は中心静脈栄養を実施するときには十分意識しておかなければならない。通常使用される中心静脈栄養は組成上、10-20%程度の糖を含んでいるため、静脈内に直接かつ継続的に投与されることにより、高血糖状態が維持されることになる。したがって定期的な血糖値、尿糖、尿中ケトン測定が必要となる。TPN導入時や不安定な病態下では、1日に1回の血糖測定を行うが、安定していれば数日に1度でもよい。なお高血糖を呈する状況下(糖尿病、高齢者、ステロイド常用、多臓器不全、敗血症、手術後、進行癌患者など)では簡単に高血糖となるため特に注意が必要である。比較的ゆるい血糖管理としてグルコース10gに対してインスリン(ヒューマリンR®)1単位を目安として開始することにより現実的な血糖管理が可能である(およそ血糖200mg/dl以下)。それでも血糖が200mg/dLを超える場合は、グルコース5gに対してインスリン1単位、2.5gに対し1単位と厳格化する。
血糖が300〜400mg/dL以上の高血糖が持続した場合、高浸透圧性非ケトン性昏睡(HONK)に陥ることがある。投与されたブドウ糖量が耐糖能を超え、インスリン不足から500mh/dL以上の高血糖、350mOsm/L以上の高浸透圧症となり、細胞内脱水、ケトーシスを伴わない昏睡などの中枢神経症状を呈する。TPN施行中に意識障害があった場合の原因の1つとして念頭に置いておくべき病態である。
一方、低血糖は突然TPNを中止された場合、相対的高インスリン血症となるため、反応性に起こりうる。具体的にはラインを外出などのためにロックするときである。高血糖よりも低血糖のほうが致死的になり得る病態なので患者にも十分な注意喚起を推奨する。また中心静脈栄養は非生理的な栄養方法であり、生体を順応させていく必要がある。開始するときも中止するときも段階的に糖濃度を変えていくように心がけるべきである。2~3日ごとに濃度を変化させていくことで安全にTPNを施行できる。
2.2 脂質関連(必須脂肪酸欠乏症、高トリグリセリド血症)
エネルギー源として糖以外では脂肪が非常に効率的に投与できる。また必須脂肪酸摂取などの点からも脂肪乳剤で全体投与エネルギー量の20%~30%を投与すべきである。
しかし脂肪を投与しないTPNではリノール酸、リノレン酸とその代謝産物である必須脂肪酸が欠乏し、3〜4週間でその症状が出現する。具体的には魚鱗癬様の皮膚症状、脂肪肝、血小板減少、創傷治癒遅延などである。これを予防するためにも、投与エネルギーの最低3〜4%程度が必要と言われており、成人では20%脂肪乳剤100mlを週3回程度投与すれば予防可能とされる。
脂肪乳剤は投与速度が速すぎると、代謝能力が追いつかず高トリグリセリド血症になる可能性がある。従って可能な限りゆっくりと投与することが必要である。20%脂肪乳剤が汎用されているが、投与速度を0.1g/kg/hr以下に設定すべきである。
おおよそ体重50kgの成人では5g/hr以下の脂肪投与速度となる。20%脂肪乳剤は100mL製剤だから脂肪含有量は20gであり、つまり4時間程度かけて点滴をする。これは25ml/hr以下の投与速度である。このことから20%脂肪乳剤の場合は体重÷2mL/hr以下の速度で、10%脂肪乳剤の場合は体重以下の速度で投与すればよいことになる。
脂肪乳剤の過剰投与は肝臓の脂肪変性を引き起こす可能性がある。過剰な糖、グリコーゲンが肝細胞内に蓄積することにより肝臓が腫大する。血液学的には肝機能関連数値に異常が認められる。脂肪乳剤を適宜組み合わせてエネルギーを確保しつつ糖投与の総量を減じることで対応することを推奨する。
呼吸不全がある場合、二酸化炭素の発生は不利な状況である。糖に頼ったエネルギー投与は二酸化炭素の発生を助長するので注意する。この場合、脂肪をエネルギーとして投与することにより二酸化炭素の発生を最小限に抑えることができる。
2.3 微量元素関連
ヒトの必須微量元素は鉄、銅、亜鉛、マンガン、ヨウ素とセレン、クロム、モリブデン、コバルトの9種類である。現在、我が国で市販されているTPN用複合微量元素製剤は鉄、銅、亜鉛、マンガン、ヨウ素の5種類しか入っていない。従ってその製剤を投与していれば、その元素に限っては欠乏症にはなりにくい。セレンについては、長期TPN施行症例において、心不全などの致死的な欠乏症が報告され、近年セレン製剤は市販されるにいたったので、6種類の微量元素に対する対応はしやすくなった。しかし残りの3種類の微量元素は対応はされておらず、欠乏症を生ずる可能性がある。またTPN用複合微量元素製剤やキット製剤に含まれる微量元素は一定量であり、微調整がきかないため、過剰症も起こりうる。将来的には各微量元素の単剤製品が市販されることを期待する。いずれにしてもTPN施行中には適切なタイミングでのモニタリング(TPN導入期:1ヵ月毎、安定期:3−6ヵ月毎)が重要であり、それが欠乏症や過剰症を予防出来る唯一の方法と言っても過言ではない1)。
2.4 ビタミン関連
TPN施行時のビタミン欠乏に関しては、現在市販されているTPN用総合ビタミン剤を投与していれば、欠乏症は生じない。しかし投与されていない場合、重篤な欠乏症を生ずる可能性ある。とくにビタミンB1欠乏症が問題となる。ビタミンB1は体内貯蔵量が少ない水溶性ビタミンであり、代謝性を惹起するので注意が必要である。ビタミンB1欠乏下ではアセチルCoAへの代謝(好気的解糖)が抑制されて、ピルビン酸が乳酸に代謝される(嫌気的解糖)ことで乳酸アシドーシスを起こす。食欲低下、悪心・嘔吐、腹痛、などの消化器症状、Kussmaul大呼吸(大呼吸により、PCO2を低下させ、アシドーシスを是正するため)、意識障害などが出現する。最近ではビタミン投与が当たり前になったこと、またワンバッグ製剤の普及によりビタミン欠乏の危険性はなくなったものの、ビタミンB1不足によって死亡例も発生しているので、必ず覚えておかねばならない欠乏症である。
3.感染
3.1 全身的カテーテル感染(カテーテル関連血流感染症)
カテーテル関連血流感染症(catheter-related blood stream infection: CRBSI)は、血管内カテーテルに関連して発生する血流感染である。急激に起こる発熱、全身の寒気、悪寒、振戦などの激烈な感染症状を呈する。血圧低下などの敗血症性ショックといたる症例もおり、迅速な対応を要する。どんなに予防策を講じても、全く皆無にすることはできず、TPN施行時にはまず対応を熟知している必要がある。
CRBSIには微生物学的CRBSI(MCRBSI)、臨床的CRBSI(CCRBSI), カテーテル関係血流感染症(CABSI)に大別される2)。MCRBSIは、「ほかに明らかな感染源がなく、カテーテル先端培養で微生物が検出される。臨床的はカテーテル抜去により感染徴候が消退する」ものをいう。CCRBSIは、「カテーテルを抜去により感染徴候が消退するが、カテーテル先端培養では陰性、または未提出。血液培養の結果とは合致しなくても、臨床的症状の消退をみれば、この範疇に入れる。」ものであり、CABSIは、「カテーテルを抜去しても感染徴候は消退せず、全身性感染徴候が持続している。カテーテル先端培養は陽性の場合も、陰性の場合もある。感染徴候が出現する48時間以内にカテーテルが留置されている場合、この範疇に入れる。全身的感染症に対する治療が必要である。」とされる。
実際、本邦では、「高カロリー輸液施行中に発熱、白血球増多、核の左方移動、耐糖能の低下など、感染症を疑わしめる症状があって、中心静脈カテーテルの抜去によって解熱、その他の臨床所見の改善をみた場合2)」が最も受け入れられている概念である。
CRBSIへの対応は、「確定診断の有無を問わず、直ちにカテーテルを抜去する」ことが原則である。抗菌薬の全身投与を行いながら、ほかの感染源がないかを検索する。CRBSIを疑っているものの、どうしても確証が得られない場合、カテーテルを一度ロックしてみると解熱することがある。治癒してない場合、カテーテルからの輸液を再開すると再度発熱する。
抗菌薬・抗真菌薬の投与は全身投与が原則である。Coagulase-negative Staphylococciが関連したCRBSIでは5〜10日、合併症のないStaphylococcus aureusに関連したCRBSIでは10〜14日、深在性の感染症(心内膜炎、敗血症性血栓症)を有するCRBSIでは抗菌薬による治療を4から6週間継続する必要がある2)。
真菌の場合は抗真菌薬を投与するが、深在性真菌症に陥るケースも少なくないため、全身検索をしっかりと行う。特に真菌性眼内炎の発生に注意を要するため、眼科的診察を必ず行う。
しかし現実的には重篤な腸管不全の症例に対する長期TPNなどでは、カテーテルを抜去せずに継続的に使用することが試みられる。「CRBSIが疑われたら即カテーテル抜去」という本来の考え方とは反するため、安易にすすめられないが、かかる症例にはライフラインとしての役割もあるので、十分な知識と観察をもって、抗菌薬の全身投与、抗菌薬ロック療法、エタノールロック療法、同部位からのカテーテルの入れ替えによる治療(Fibrin sheath法)などが行われているのが現状である。
CRBSIについて最も大切なことは予防することである。そのためにも正しい知識の普及、適切な管理が重要である。適切なカテーテルとルーメン数、留置方法の選択、輸液ラインの無菌的管理、輸液の無菌的管理、カテーテル挿入部のドレッシング管理などである。NSTやICTなどの専門チームがCVCを管理することで、感染率が低下することが知られており、院内でチーム医療の一環として、管理されることが望まれる。
3.2 局所的カテーテル感染
局所的カテーテル感染とはカテーテル周囲局所の感染を指す。局所の炎症所見はあるものの、全身状態は良好であり、発熱や炎症反応が少ないことが多い。局所の処置や抗生剤の投与で軽快することもあるが、再感染を起こし、最終的に抜去、再挿入が必要になることも多い。
文献
- 上原秀一郎 ほか : 外科と代謝・栄養 49 :67-72, 2015
- 日本静脈経腸栄養学会(編):静脈経腸栄養ガイドライン、第3版、p91, 2011



