- PDNレクチャーとは?
- Chapter1 PEG
- 1.胃瘻とは
- 2.適応と禁忌
- 2.1 適応と禁忌
- 2.2 疾患別PEG適応
- ①パーキンソン病
- ②アルツハイマー病
- ③頭頸部癌
- ④ALS
- ⑤認知症
- ⑥脳血管障害
- ⑦食道がん
- 3.造設
- ①分類
- ②Pull・Push法
- ③Introducer原法
- ④Introducer変法
- ⑤胃壁固定
- 3.2 術前術後管理
- 3.3 クリティカルパス
- 4.交換
- 4.1 カテーテルの種類と交換
- 4.2 交換手技
- 4.3 確認方法
- ①交換後の確認方法
- ②スカイブルー法
- 4.4 地域連携・パス
- 5.日常管理
- 5.1 カテーテル管理
- 5.2 スキンケア
- 6.合併症・トラブル
- 6.1 造設時
- ①出血
- ②他臓器穿刺
- ③腹膜炎
- ④肺炎
- ⑤瘻孔感染
- ⑥早期事故抜去
- 6.2 交換時
- ①腹腔内誤挿入と誤注入
- ②その他
- 6.3 カテーテル管理
- ①バンパー埋没症候群
- ②ボールバルブ症候群
- ③事故抜去
- ④胃潰瘍
- 6.4 皮膚
- ①瘻孔感染
- ②肉芽
- 7.その他経腸栄養アクセス
- 7.1 PTEG
- 7.2 その他
- ●「PEG(胃瘻)」関連製品一覧
- Chapter2 経腸栄養
- Chapter3 静脈栄養
- Chapter4 摂食・嚥下リハビリ
- PDNレクチャーご利用にあたって

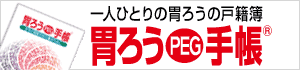
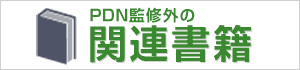

1.適応
小児は成長・発達する。このため適切な栄養が不可欠であり、その提供は養育者の義務となる。逆に適切な栄養が提供されない場合は虐待となる可能性があり、注意が必要である。このため、小児においては経口摂取が困難である場合、全例経管栄養法の適応となり、長期的な経管栄養が必要な場合は胃瘻が第一選択となる。(図1)
しかしながら、小児においては胃瘻・腸瘻の適応でありながら、造設に至らないケースも多々存在する。これに伴い、乳児期から年単位の長期にわたり経鼻経管栄養(経鼻胃管,経鼻EDチューブ)が継続されることがある。
この原因として、
①小児における胃瘻造設時期の適切なガイドラインが存在しない。
②主治医(多くは小児内科医)の知識不足
③造設可能な医師が近くにいない。
④保護者の拒否
などが挙げられる。
①、②について、ガイドラインの作成は急務であり、また、ガイドラインの存在は胃瘻に対して嫌悪感や恐怖感をもつ保護者への説明において、強力な武器となることは間違いない。また、ガイドライン等で適切な知識を流布することで、胃瘻・腸瘻についての知識を多く持たない主治医(小児内科医)を後押しすることができればと考える。
特に「まだかわいそう」や「もう少し大きくなってから・・・」と問題を先送りする医師に対して、その間違った考え方を払拭させたいと考えている。(図2)
1)小児の胃瘻では造設を行う診療科はほとんどの場合小児科(小児内科)ではない。造設は小児外科が担当することが多く、地域によっては小児外科の確保が困難で、消化器外科・消化器内科が担当する場合もある。
近年、腹腔鏡補助下胃瘻造設術(LAPEG)が行われるようになり、乳児期に造設される症例も増加している。しかしながら、小児を専門としない医師にとって、乳児の造設はリスクが高く、成長を待たざるを得ないこともある。
2)一部には胃瘻への嫌悪感が強く、造設を断固として拒否する保護者も存在する。
過去に行われた胃瘻バッシングの影響もあるが、医療関係者(介護職など)で高齢者の胃瘻を見ている保護者が、それを見て拒否する場合もある。
また、小児で経管栄養を必要とする児の多くは重症心身障害児である。これら重症児では、以前より保護者同士のつながりが強固であり、全国単位のものから地域におけるものまで幅広い。これらネットワークでは、必ずと言っても過言ではないほど「ボス」「インフルエンサー」などの強者が存在し、その影響を受けている事もある。(図3)
2.造設
2-1.造設と狭義の適応
ここでは狭義の適応として、胃瘻・腸瘻等の投与経路別に適応を考えていく。
小児における造設でポイントとなるのは以下の3点である。
1)消化管の先天的閉鎖
基本的に外科手術の適応となる場合が多く、胃瘻が必要な場合、手術時に同時に開腹造設やLAPEGを行うことが多い。
2)胃食道逆流症(GERD)
小児、特に重症心身障害児ではてんかんの合併や筋緊張が亢進により、GERDを合併することが多い。治療の第一選択は噴門形成術であるが、術後も筋緊張に負けて逆流が再発する症例も散見される。
経管栄養を開始するにあたり、逆流がみられるようであれば、可能であれば経鼻EDチューブで栄養を開始し、胃瘻の造設後は逆流の程度によって、半固形化栄養剤の使用や経胃瘻的空腸チューブ(PEG-J)への変更を考慮する。
3)身体変形
特に重症心身障害児において、脊椎側弯や筋緊張亢進により身体変形がみられることが多い。横方向の側弯では胃が挙上され胸郭内に入ってしまうことも多い。この場合、内視鏡的造設が困難であることが多く、開腹造設やLAPEGの適応となる事が多い。しかしながら、年長児かつ保護者が大きな侵襲を好まない場合は経皮的経食道胃管(PTEG)造設を行う場合もある。
2-2.胃瘻造設
乳幼児期では全身麻酔下に行う腹腔鏡補助下胃瘻造設術(LAPEG)が安全な方法として確立している。
しかしながら、局所麻酔+鎮静による内視鏡的胃瘻造設術(PEG)も不可能ではない。細径(経鼻)内視鏡の経口挿入が可能であれば造設は可能となる。
筆者らは体重6㎏以上、かつ、術前検査(後述)で内視鏡的造設が可能であると判断した症例には細径内視鏡(経鼻内視鏡)を経口挿入し、積極的に内視鏡的造設を行っている。(図4)
PEGはイントロデューサー法(原法・変法)で行い、Pull・Push法は食道損傷の危険性が高いため、乳幼児および年少児には原則として行ってはならない。
PEGが不可能な症例で開腹造設を行う症例もあるが、開腹造設は多くの場合、他の開腹手術と並行して行うことがほとんどであり、積極的には行わない。
2-3.腸瘻造設
小児において、腸瘻造設となる症例は非常に少ない。特に重症心身障害児で筋緊張亢進がみられる患者に腸瘻造設を行った場合、腸液が漏出し重篤な皮膚障害を引き起こすことがある。このため、筆者らは長期管理が必要な小児において、やむを得ない理由がない限り、積極的に腸瘻造設を行うことはない。
やむを得ず造設を行う場合、多くは開腹造設であり、他の術式と並行して行われることがほとんどである。
2-4.その他
1)一期的PEG-J造設術
GERD合併例では噴門形成術と同時にPEG造設を行う場合が多いが、大きな侵襲を嫌う場合など、PEGを行い、PEG-Jカテーテルを挿入する一期的PEG-J造設を行うことがある。
内視鏡的にイントロデューサー変法を用いて瘻孔を確保し、瘻孔よりガイドワイヤーを挿入し、造設に用いた内視鏡で空腸まで牽引し、一期的にカテーテルを空腸まで挿入する。X線透視下での挿入も不可能ではないが、内視鏡を用いた方が容易に空腸までガイドワイヤーを挿入できる。また、一期的造設においてオリンパス社の造設キット、特にシースイントロデューサーを使用することで、患者侵襲をより少なく造設することが可能である。
2)PTEG
PEGが困難な小児に対してPTEG造設を行うことがある。乳幼児では穿刺部が非常に狭く困難であることも多い。特に身体変形が強い年長児で、大きな侵襲を嫌う症例の場合、空腸投与も可能なPTEGは非常に有用な手技である。
造設は成人と同様であり、PTEGの項をご参照されたい。
(参考)胃腹壁固定
イントロデューサー法を用いたPEGでは、胃腹壁固定が必須である。
筆者は穿刺スペースが取れない場合を除き、いわゆる鮒田型胃腹壁固定器具を用いて、瘻孔部を四角く取り囲むように4点固定としている。
造設完了後、4~6時間で頭側および尾側の固定糸を抜去し、左右2点の固定糸は感染などのトラブルがない限り、初回カテーテル交換時まで残すようにしている。
これは造設直後に事故抜去が起きた際に、再挿入(ほぼ再造設に近い事が多い)を容易にするためである。(図5)
2-5.造設時期
前述したが、小児では漫然と長期に渡る経鼻経管栄養が続けられている事がある。
長期の経鼻経管栄養はデメリットが非常に多く、避けるべきである。(図6)
生下時からの経口摂取困難時では乳児期に造設を行うことが推奨される。(図7)
しかしながら、一部の大学病院や専門医療機関以外では、乳児期は経鼻経管栄養を選択し、成長を待って造設を検討する症例も多い。
成長面および学校等でのケア、および成長に伴う身体変形等を考慮すると、小学校入学前までに造設を行うことが望ましい。(図8)
重症心身障害児(者)の造設時期は二峰性がみられ、生下時からの経口摂取困難例については小学校入学前(3~5歳)が最も多く、経口摂取が可能であった症例では、摂食,嚥下機能の低下により、30代後半から40代で経管栄養導入され造設に至る症例が多い。(図9・10)
(参考)長期間の経鼻経管栄養による合併症:鼻翼の褥瘡 経鼻チューブの固定方法が悪いと鼻翼の血流が悪くなり褥瘡を生じる場合がある。 最悪、完全に鼻翼が裂けてしまう症例も存在し、縫合を行ってもなかなか癒着せず、治療に難渋することがある。(図11)
3.カテーテルの選択
小児では12~14Fr程度の細いバルン型カテーテルが選択される事が多い。
しかしながら、これら細いカテーテルは造設早期からカテーテル閉塞などのトラブルに見舞われる事があり、推奨できない。
欧米では乳児であっても24Frカテーテルが使用されることが多く、筆者らも24Frカテーテルでの造設を行っているが、これまで大きな合併症等を生じたことはない。(図12・13・14)
内部ストッパーについて、必ずしもバルン型である必要性はない。現在はバンパー型でも交換時の痛みがほぼゼロであることをセールスポイントとしたものがあり、児のADLや生活の場などに応じた選択を行う必要がある。
半固形化栄養法を用いる場合、可能であれば16Fr以上のカテーテルを推奨する。また、ミキサー食注入を行う場合は20Fr以上を推奨する。細いカテーテルで造設が行われている場合には瘻孔を少しずつ拡張し、16Frまたは20Frまでサイズアップを行う。多くの症例でワンサイズアップ(12→14等)であれば拡張器具を用いず挿入することが可能な場合が多いが、必ず瘻孔破損による腹腔内誤挿入がないことを確認しなければならない。
また、バンパー型カテーテルで逆流防止弁が胃側にあるものについて、逆流防止弁が抵抗となるため推奨されない。
後述するが、経胃瘻的内視鏡(PEGスコープ)を使用するためには、16Fr以上のカテーテルが必要(一部メーカーでは18Fr以上推奨)である。
なお、筆者らは造設を24Frバンパー型(オリンパス社イディアルボタン)で行い、初回交換時に以降もバンパー型を用いる場合は、24FrのイディアルボタンZEROを使用し、バルン型に変更する場合は20Frバルン型(富士システムズ社GBバルンボタンシリーズ)を用いている。
また、半固形化栄養法およびミキサー食を使用する児については、富士システムズ社製ラージボアⅠを用いている。ISO規格の新型カテーテルの中では異色の製品であるが、888規格への変換コネクタ等を用いなければ、現存するISO規格製品の中では注入が楽にできるカテーテルであると思われる。
(参考)カテーテルサイズアップの手法と拡張器について
前述したとおり、多くの患児でシャフトの太さ1サイズアップの場合、ほぼ難なく挿入が可能であるが、筆者はサイズ変更前のカテーテルを抜去する際に、バルン型であればバルン水を1ml程度残して拡張しながら抜去する。また、それでもきつさを感じる場合は、子宮頚管ブジーを用いて機械的に瘻孔を拡張し、挿入を行っている。(図15)
4.カテーテル交換
交換手技自体は他項で詳細説明されているのでそちらをご参照されたい。
小児では、交換に際し毎回経鼻・経口内視鏡を使用することは不可能に等しい。
このため、交換後確認はスカイブルー法や造影剤による間接確認、または、経胃瘻カテーテル内視鏡(PEGスコープ)を用いた直接確認を行う。
筆者らは16Fr以上のカテーテルを使用する児(バラードMIC-KEY等一部のカテーテルについては18Fr以上推奨)については前例PEGスコープによる確認を行っている。また、12・14Frカテーテル使用中の児については、スカイブルー法を用い、陰性の場合のみ希釈造影剤を用いたX線透視検査を行い、確実に胃内に挿入されていることを確認している。
5.合併症・トラブルシューティング
ここでは経管栄養児によくみられる合併症とその対処法について紹介する。
5-1早期合併症
1)ビタミンK欠乏性出血
造設早期の出血について、胃内からの出血ではなく、胃腹壁固定糸の糸穴や瘻孔部の皮膚からじわじわした出血が続くことがある。
特に、造設前長期にわたり経腸栄養剤を使用されていた症例で見られ、多くの場合、ビタミンKの欠乏による出血であることが多い。
対処法:造設前にケイツーを投与しておく。
2)カテーテル閉塞
16Fr以上のカテーテルを使用している場合には少ないが、12,14Frカテーテルで生じることがある。閉塞原因としては酸化マグネシウム(散薬),各種漢方薬が多い。
また、チューブ型カテーテルで造設を行っている場合、外部ストッパーを皮膚に結紮している症例を見かけることが多いが、この際に固定を強固にするためか、シャフトに固定糸を何重にも巻き付けている症例を見かける。この巻き付け部でシャフトが狭くなり閉塞することがあるため、太いカテーテルであってもシャフトに固定糸を巻き付けている場合は、この部分を疑ってみる必要があることを付け加えておく。
対処法:薬剤は極力散薬を用いず、錠剤の簡易懸濁法を試みる。
チューブ型カテーテルの場合、外部ストッパーの固定糸がシャフトに巻き付いていないか確認し、巻き付いている場合、まずは固定糸を除去してみる。(それだけで閉塞解除することがある。)
3)事故抜去
造設早期の事故抜去は瘻孔も完成していないため、再挿入困難な場合も多い
。
また、小児の場合、瘻孔の閉鎖するスピードも速く、カテーテルが抜けて一晩経過してしまった症例では、瘻孔が完全に閉鎖していることもある。
対処法
(0)事故抜去が懸念される児(特に手の自由度が高い児やハイハイ移動を行う児)では、腹巻等による保護、ミトン型手袋の使用などの事前対策が必要である。
(1)保護者に対し、事故抜去時の対応をきちんと説明(マニュアルがあればなおよい)した上で、抜去時に挿入するカテーテル(ネラトンカテーテルや尿道カテーテルでもよいが、絶対に栄養注入しないよう指導しておく。)を渡しておき、直ちに医療機関を受診するよう指導する。
(2)瘻孔が保持されていれば再挿入を試みる。この際、瘻孔が狭小化している場合、サイズアップの項を参考に拡張器で拡張しても良い。
(3)瘻孔閉鎖が進んでいる場合、ガイドワイヤーが通過可能な瘻孔が残っていれば、内視鏡下にガイドワイヤーを挿入し、造設キット付属のダイレーターで拡張を行い、カテーテルを再挿入する。この時、胃腹壁固定糸が残存していれば、追加で胃腹壁固定を行う必要はないが、既に抜去されている場合には、造設時と同様に胃腹壁固定を行っておくべきである。
瘻孔が完全に閉鎖し、ガイドワイヤーも通過できなければ、再造設を行う以外に方法はない。
5-2.長期合併症
漏れて炎症を起こした皮膚のケアについてはカテーテル管理の項を参照されたい。
小児では成人よりも消化管瘻の留置期間が長く、10年単位となる事も少なくない。
長期合併症で最も多いのは瘻孔拡大,瘻孔からの漏れといった瘻孔トラブルである。
特に、てんかん,筋緊張亢進の見られる重症心身障害児では腹圧が高くなりがちであり、瘻孔拡大や瘻孔漏れを増悪させる要因になりうる。(図16)
1)瘻孔拡大と瘻孔部からの漏れ
瘻孔拡大について、瘻孔が拡大したからと太いシャフトのカテーテルに変更するのは間違った対処である。まずは拡大した原因を検索し、適切な対処が必要である。
瘻孔部からの漏れについて、シャフト長を短くして、内部ストッパーと外部ストッパーで胃と腹壁を挟んで漏れを止めようとする医師(特に小児内科医)は多いが、これは間違った処置である。挟み込んでしまうと胃と腹壁が菲薄になり、一時的な改善はみられても必ず増悪する。(図17・18)
2)対処法
(1)てんかん,筋緊張亢進等に対する治療を行う。
長期管理される重症児で痙攣が頻回な児では、特に短時間(5分以内)の痙攣発作は見守りのみで経過観察されることも多い。しかし、これにより腹圧が亢進し、漏れなどが発生している場合には、抗てんかん薬等の見直し等も検討する価値はある。
(2)カテーテルの角度やシャフト長の見直しを行う。
瘻孔拡大に対していたずらに太いシャフトに変更しない。
シャフト長を短くして胃と腹壁を挟み込まない。逆に外部ストッパーと腹壁までの距離を十分に取り、瘻孔部の腹壁の厚さを増していくことが必要である。
乳幼児期など腹臥位で移動する(ハイハイやいざり移動)場合には、カテーテルが引っ張られて瘻孔拡大,瘻孔漏れにつながる場合もあり、腹巻等での保護も有用である。
(3)カテーテルを一時的に抜去し、瘻孔を収縮させる。ただし、抜去により胃内容が漏出するため、皮膚トラブルに注意が必要である。
(4)胃内を持続的に吸引し減圧する。
カテーテル開放や用手での減圧には限界がある。このため、一時的にPEG-Jカテーテルを使用し、栄養剤を空腸投与に変更した上で、胃側ルーメンを吸引機で間欠持続吸引とする。
この方法は重度の瘻孔拡大,瘻孔漏れ、それに伴う皮膚トラブルには非常に有効な方法であるが、在宅患者では一時的に入院加療となる事もあり、ハードルが高い方法でもある。
(5)瘻孔閉鎖と再造設
造設部位は胃体部が望ましいが、それ以外、特に幽門付近の造設であればボールバルブ症候群を惹起したり、空腸への流出障害が発生し腹圧が高まり、漏れにつながる場合がある。また、胃を牽引して大彎側に造設すると漏れが発生する場合が多い。これら造設部位に起因する漏れの場合は、現在の瘻孔を閉鎖し、新規に造設することも検討する。
しかしながら、造設から年数の経過した瘻孔、特に大彎部の瘻孔では、完全な自然閉鎖が不可能で、ピンホールのような小さな孔が残存、それが再拡大するといった場合もある。
(参考)
筆者らは瘻孔トラブルの重症症例に様々な手法で瘻孔閉鎖を試みたが、最も確実性が高いのは旧瘻孔を含めた胃の一部を部分切除する方法であった。しかしながら、この方法は開腹手術であり、侵襲も高くハードルは高い。
次点として、ある程度の時間はかかるものの、経鼻WEDチューブを用いた空腸投与と胃内間欠持続吸引が効果的であった。
逆に瘻孔部を縫合したりする方法は、手間の割に効果がなく推奨されない。
6.最後に
小児のPEGは決して恐ろしいものではなく、使用する児のQOLを向上させ、本人のみならず保護者,その他の介護者をも笑顔にできる可能性を秘めている。 正しい知識を持って、積極的に取り組んでもらいたいと考えている。



